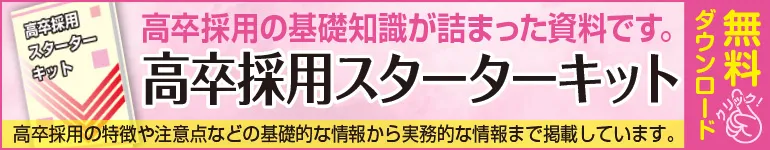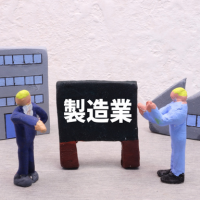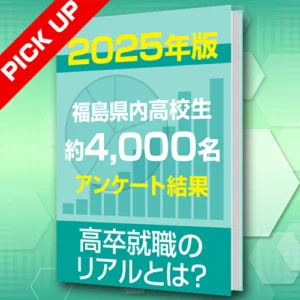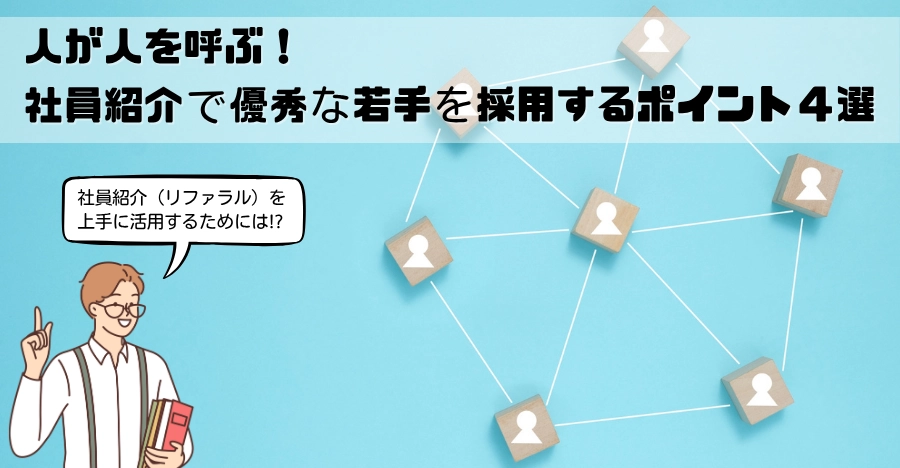
少子高齢化に伴う生産人口の減少により、優秀な若手人材の採用は難しくなる一方です。そんな中、信頼性と定着率の高いリファラル採用が注目を集めています。今回は、リファラル採用に基本や仕組み、運用の手順、成功のポイントについてのお話です。
目 次
1.はじめに
2.リファラル採用とは
3.リファラル採用運用の5つの手順
4.優秀な若手を集めるための4つのポイント
5.まとめ
1.はじめに
近年、多くの企業が人材獲得競争の激化に直面しています。とりわけ、優秀な若手人材の採用は難易度が高く、従来の求人広告や人材紹介会社頼りでは十分な成果が得られないこともしばしばです。そこで注目されているのが「リファラル採用」。既存社員からの紹介によって信頼できる候補者を獲得する仕組みは、コスト効率がよく、定着率も高いと評価されています。本記事では、リファラル採用の基本と運用の流れ、そして特に「優秀な若手を集める」ためのポイントに焦点を当て、効果的な仕組みづくりのヒントを解説します。
2.リファラル採用とは
リファラル採用とは、社員から知人・友人を自社に紹介してもらい採用につなげる手法です。自社をよく知る人物との信頼関係をベースとした採用であるため、企業文化とのマッチ度が高く、ミスマッチによる早期離職が起こりにくいのが特長です。また、採用コストが抑えられる点や、社員が紹介者として能動的に関与することで、組織全体のエンゲージメント向上にもつながります。近年は制度化し紹介報酬などのインセンティブを導入する企業も増え、戦略的な採用手法として浸透しつつあります。
「縁故採用」と似ている部分はありますが、来るもの拒まず採用するというわけではなく、自社の求める人材であるかはしっかりと精査し、採用基準を満たした者のみを採用するという大きな違いがあります。
以下に、リファラル採用運用の手順「①~⑤」それぞれの説明文を充実させた内容をご提案します。
3.リファラル採用運用の手5つの手順
リファラル採用を制度として社内に導入・定着させるためには、段階的な手順と社内全体の理解が不可欠です。以下は、導入から運用・改善までの基本的な手順です。
① 社内周知と理解の促進
リファラル採用の第一歩は、制度の趣旨や目的を社内に明確に伝え、社員の理解と協力を得ることです。
・なぜリファラル採用を導入するのか
・どのような人物を求めているのか
といった背景や方針を丁寧に説明することで、社員が自らの役割を理解し、積極的に関わろうとする姿勢が育まれます。経営層や人事担当者からのメッセージを含めた説明会の開催や、社内に向けた継続的な情報発信、成功事例の共有など、自社に合った周知方法で、「リファラルは特別な人だけが行うものではなく、全社員が参加できる制度である」と認識してもらうことが成功への第一歩です。
② 紹介しやすい仕組み・制度作り
紹介が面倒だったり手続きが複雑だったりすると、制度がうまく活用されなくなってしまう恐れがあります。社員が気軽に候補者を紹介できるようにすることが大切であり、「紹介しやすさ=スピードと手軽さの両立」を実現するため施策を取り入れることがおすすめです。以下は、施策の一例です。
・Googleフォームや社内アプリで簡単に推薦できる入力フォームの設置
・SlackやLINEなど、社員が日常的に使うツールと連携させた申請方法の導入
・「カジュアル面談あり」「履歴書不要」など、候補者側の心理的ハードルを下げるオプションの用意
・社員が候補者に制度を案内しやすくなるような紹介用テンプレート・資料の配布
制度設計時には、実際に利用する社員の声を取り入れ、「現場視点」での改善を繰り返すことが重要です。
③ インセンティブ設計
リファラル制度を社内に根付かせるためには、「紹介したくなる仕組み」を用意することが必要です。インセンティブはその鍵となるポイントであり、社員の参加意欲を後押しする効果があります。インセンティブの例としては以下が考えられます。
・採用成功時に一定額の報奨金
・紹介数や実績に応じたポイント制の導入
・社内表彰や評価制度への反映
・「社内ランチ招待」「記念品贈呈」など金銭以外の報酬
特に若手社員に向けては、「社内で評価されている」「会社に貢献できている」と実感できる仕組みにすることで参加率アップが期待できます。
④ 選考プロセスの整備
紹介された候補者がスムーズに選考を受けられるよう、明確で一貫性のあるプロセスを整備します。制度の信頼性維持のため、紹介した社員に対しても進捗が見える状態を保つ仕組みも忘れずに取り入れましょう。リファラル専用の選考ルートやカジュアル面談やオンライン面談など柔軟な対応方法の導入、選考状況を紹介者に共有するタイミング・方法の明文化など、リファラル採用特化の選考プロセスを整えると良いでしょう。また、紹介者・候補者双方からフィードバックを収集して次の採用活動に生かすことで、より良い選考体験が提供できるようになり制度の信頼度が高まります。
⑤ 効果測定と改善
導入したリファラル制度の成果を定量的・定性的に評価し、PDCAを回していくことが制度の定着・発展に欠かせません。主に確認すべきポイントは以下の通りです。
・紹介件数(月別・部署別・社員別)
・採用決定数と成功率(紹介者数/採用者数)
・入社後の定着率(3ヶ月・6ヶ月・1年後の在籍率)
・社員の制度認知度と満足度(社内アンケートによる調査)
・紹介者と候補者からのフィードバック内容
これらのデータを分析し、「どの部署が活発に動いているか」「どの部分で離脱しているか」などの傾向を見極め、制度の改善につなげましょう。分析結果を社内に共有することで、制度の透明性と信頼性が高まりさらなる参加促進にもつながります。
4.優秀な若手を集めるための4つのポイント
優秀な若手人材をリファラルで集めるには、単に制度を導入するだけでなく、社員が「紹介したくなる」環境と「紹介されたい」と思われる企業イメージの両方が必要です。以下の4つのポイントを意識することで、より質の高い成果が期待できます。
① 紹介したくなる会社づくり
まず大切なのは、紹介する社員自身が「この会社を人に薦めたい」と心から思えるような職場環境や企業文化を築くことです。職場に満足していない社員は、自分の大切な知人を紹介しようとは思いません。紹介とは、信頼の延長線上にある行動だからです。そのためには、働きがいのある制度の整備や社内コミュニケーションの活性化、経営層が社員の声に耳を傾ける文化づくりなどが大切です。
② 候補者への魅力発信
若手人材が企業に関心を持つためには、その企業が提供できる「魅力的な成長環境」や「働く意義」が明確であることが大切です。特に20代・30代前半の若手人材は、報酬よりも成長機会や働き方の柔軟性を重視する傾向があります。特に
・若手がチャレンジできるプロジェクトや役割、キャリアパスの明示
・教育、研修制度やOJT体制の説明資料
・ワークライフバランスを重視した制度の紹介
・実際に活躍している若手社員のインタビューやストーリー
などは、若い人材が知りたい情報ですので積極的に発信しましょう。
③ 紹介ハードルを下げる
社員が「紹介してみようかな」と思えるようにするには、紹介に対する心理的・手続き的ハードルを下げることが不可欠です。リファラル制度があっても、手続きが面倒だったり、紹介後の負担が大きいと感じられると、実際にはほとんど活用されません。
気軽に紹介できる仕組みや紹介マニュアル・FAQを整備しておくことで、社員が安心して第一歩を踏み出せるようになります。
④ 若手社員の活用
若手人材をターゲットとしたリファラル採用では、すでに活躍している若手社員の力を借りることが非常に効果的です。同世代であることにより価値観や就職観も近く、紹介先の候補者に対して自然な共感やリアルな情報提供が可能になります。若手社員向けの「紹介キャンペーン」などの企画や、オンライン座談会など紹介前のラフな接点づくりを実施することで自社の若手社員を巻き込みより自然な形でのリファラル活性化を狙います。
5.まとめ
リファラル採用は、制度化と運用設計によって大きな力を発揮する採用手法です。特に優秀な若手を惹きつけるには、企業の魅力を発信し、紹介しやすい環境を整えることがカギとなります。社員一人ひとりが「リクルーター」として活躍できるような仕組みを築くことで、持続可能かつ高品質な採用活動が可能になるのです。
福島採用.comでは、採用に関するお役立ちコラムの他、採用活動で使える各種ツールの相談も随時受け付けています。「新しい採用手法を取り入れたい」「若い人材を確保したい」などのお悩みがありましたら、いつでも気軽にご連絡ください。