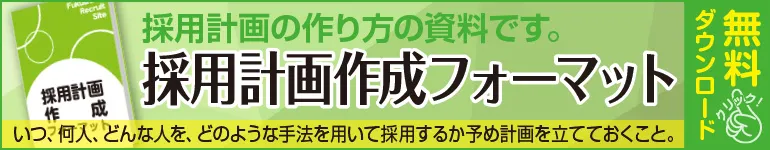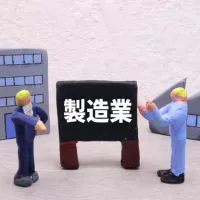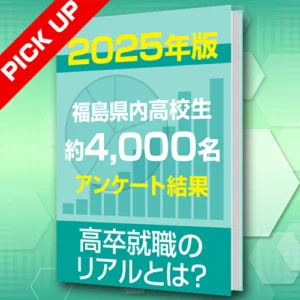人員補充のため、業務拡大のため、せっかくコストと労力をかけて雇用した人材も、早期に離職してしまってはすべてが水の泡になってしまいます。ここでは、離職率を下げ安定的に人材を定着させるために有効な方法を解説していきます。
目 次
1.はじめに
2.離職率が高くなる主な6つの原因
3.離職率を下げるため見直すべき5つのこと
4.まとめ
1.はじめに
離職率とは、従業員数に対して一定期間内で退職した人の割合のことです。厚生労働省の雇用動向調査によると、直近5年分の離職率は以下の通りです。

新型コロナウイルスの流行により一時的に増加しましたが、全体的には減少傾向にあるようです。しかし、統計上は減少しているとはいえ
・人材が定着しない
・せっかく採用したのにすぐ退職してしまう
といった悩みを抱える企業が数多く存在するのが現状です。
離職率を下げるためには、まずは離職率が高くなる原因を把握することが必要です。離職率を高くなる主な要因や離職率を下げるために有効な対策をご紹介しますので、自社に当てはまる原因や取り入れられそうな対策・方法をチェックしていきましょう。
2.離職率が高くなる主な6つの原因
① 育成やフォロー体制が不十分
業務に必要なスキルや知識を十分に身に着けることができていなかったり、分からないことや困ったことを気軽に相談できる・フォローしてくれる人がいなかったりすると、仕事でのミスや業務効率の低下につながります。これにより労働者は自信を無くし、結果として離職を選択することになります。
② 正当な評価を受けられない
労働量や成果に対して人事的な評価や賃金が低いなど、正当な評価がされていないと労働者は不満を抱き仕事に対するモチベーションが低下します。特に、賃金は生活にも直結している要素ですので一般水準よりも低い賃金で昇給も見込めないとなると離職を考えるのは当然の流れかもしれません。他にも、「残業代やボーナスが出ない」「福利厚生が充実していない」なども同じく不満を抱く原因となります。
③ 労働時間が長い・休日が少ない
法定を超える長時間労働が習慣化していたり、深夜残業や休日出勤をしないとこなせない仕事量を抱え込んだりすると、当然労働者は心身ともに疲弊し健康状態にも影響を及ぼしかねません。
④ 休暇が取りにくい
休暇が取りにくい要因は大きく分けて次の2つです。
・仕事量が多すぎて休暇を取る暇がない
・人間関係や職場の雰囲気から、休暇を取りたいことを言い出しにくい
ストレス解消やリフレッシュのためにも休暇は大切です。十分な休みが取れないと、生産性やモチベーションの低下し不満度も上がります。
⑤ 業務にミスマッチがある
・入社前に考えていた業務と違っていた
・自身の適性と合わない部署へ異動になった
など、入社前の情報不足によるミスマッチや労働者の適性を見誤ると、本来の能力が十分に発揮されず自信の低下につながります。
⑥ ハラスメントがある
セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、モラルハラスメントなど、近年様々なハラスメントが話題にあがります。「ハラスメント」とは「いやがらせ」という意味です。相手を不快にさせる行動や言動が日常的に横行しているような職場では、労働者たちは過度なストレスを抱え込み早急に離職を考えることでしょう。
3.離職率を下げるため見直すべき5つのこと
前述の6つの原因を改善し離職率を下げるために有効な対策をまとめました。
① 研修制度見直す
入社や異動後、業務に必要な知識やスキルを身に着けるための研修をしっかりと行うことで、ミスの多発やフォロー体制の不備からくる自信喪失やモチベーションの低下を防ぐとこができます。研修には、以下のようなツール等を取り入れるとより効果的です。
・研修用資料・業務マニュアル
伝える内容を網羅・明文化したツールを事前に準備しておけば、教育の質を一定化させることができます。また、研修終了後に困ったことがあっても見返すことができる資料があることは、新しい環境で仕事をする上での安心感にもつながります。
・OJT期間の導入
「On-the-Job Training」の略で、研修だけでは身に着けることが難しいスキルを実践を通して業務知識を学んでもらうために行う育成の手法です。メンターである先輩や上司からダイレクトにフィードバックを受けることができ、社内コミュニケーションの向上にもつながります。
② 賃金・待遇を見直す
労働者からのヒアリング等を実施して賃金・待遇に対する不満を把握し、企業側・労働者側の双方が納得のいく条件を出すことが大切です。賃金等が改善されることはもちろんですが、「会社は自分を見てくれている・正当に評価しようとしてくれている」ということが相手に伝わり、業務に対するモチベーションや自社へのエンゲージメントが高まります。
③ 労働時間を見直す
・労働基準法に定められている労働時間を超えて勤務していないか
・長時間の残業が続いていないか
・深夜残業や休日出勤が増えていないか
労働者の勤務時間に上記のようなケースがみられる場合は、業務量は適切であるかや業務に無駄やムラがないかを調査し改善に努めましょう。業務効率をアップしたり仕事の割り振り方を変えたりすると、労働時間の改善だけではなく人件費等のコストダウンも計ることができます。他にも年次有給休暇を取得しやすい体制や環境を整えて、良いワークライフバランスを保つことができる環境を作ることが重要です。
④ 人事制度を見直す
離職率が高くなる原因の一つに「業務のミスマッチ」がありましたが、これを改善するためにまずするべきことは人事制度の見直しです。
<採用活動時のポイント>
・欲しい人物像を明確にし、人事担当間や社内間で共有する
・募集時に公開する業務内容等の情報をより詳しくする
・応募者が従事してほしい業務に対して適性があるか見極める
<人事異動時のポイント>
・異動先への適性があるか見極める
上記のことを実施すると、労働者は「どんな業務を求められているのか」や「入社後の自分の姿」が明確になり入社後の業務のミスマッチを最小限に抑えることができます。
⑤ 社内の習慣を見直す
これまで社内で当然のようにまかり通っていた風習や振る舞い、社員同士の関わりは、本当に個々を尊重した秩序あるものだったかどうか、今一度見直してみましょう。例えば定期的なアンケートを実施すれば、隠れたハラスメントを見つけたり労働者からのヘルプを救い上げるきっかけになるかもしれません。ハラスメントのない、誰もが安心して業務ができる環境を作ることは非常に重要です。
4.まとめ
「居心地がよくて長く働き続けたい!」と思う環境を整えれば、自然と労働者は定着し離職率も下がります。まずは自社の離職率が高いのはなぜなのかを知り、その原因を解消するためにできることをひとつずつ実施していきましょう。そうすることで、離職率が下がるだけではなく企業としての魅力もさらに高まり、結果的に事業発展にも大きく貢献してくれるかもしれません。
福島採用.comでは、福島県内の企業様の「採用」をサポートするための情報発信やツールの紹介を行っています。
・優秀な人材を集めたい
・もっと効果的に自社をPRしたい
など、どんなお悩みも大歓迎ですのでぜひお気軽にお問い合わせください。