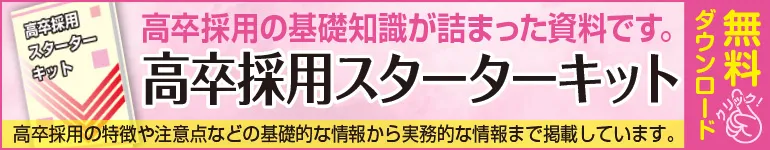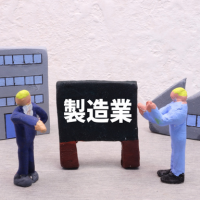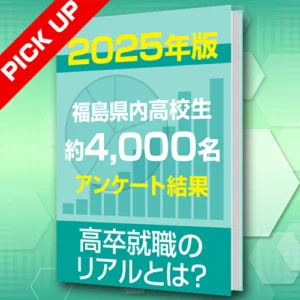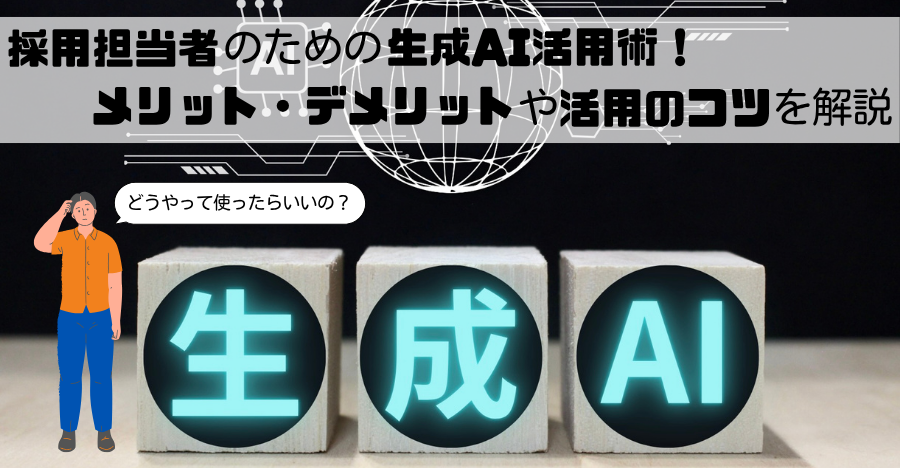
目 次
1.はじめに
2.生成AIを活用できる採用業務
3.採用業務で生成AIを使う4つのメリット
4.採用業務で生成AIを使う4つのデメリット
5.生成AI活用のコツ
6.まとめ
1.はじめに
2.生成AIを活用できる採用業務
採用活動では、求人票づくりや候補者対応、広報コンテンツの発信など様々な業務があります。効率化と質の両立が課題の採用活動において、生成AIを特に活用しやすい5つのシーンをご紹介します。
①求人票の作成・改善
求人票は、応募者にとって企業の第一印象を決めるとても重要なツールです。しかし「どんな言葉で魅力を伝えるか」「ターゲットに響くタイトルは何か」など、悩みながら作っている方も多いのではないでしょうか。生成AIを使えば、職種の特徴や企業の雰囲気をふまえたうえで様々な表現を提案してくれます。伝えたい情報は人が与え、表現はAIに広げてもらう、という形で上手に役割分担ができます。
<活用例>
・職種ごとの特徴や魅力をうまく伝える本文案
・ターゲットに響く求人タイトルのアイデア
・企業の雰囲気に合わせたトーン・文体の調整
②スカウトメール・ダイレクトリクルーティング文面の作成
候補者に直接アプローチするスカウトメールは、文面の印象が返信率を大きく左右します。ただ、毎回一から考えるのは意外と時間がかかるものですし、テンプレート的な内容になってしまうことも少なくありません。生成AIなら、候補者の経歴やスキルに応じた内容を盛り込みつつ、柔らかさや丁寧さを持った文面を提案してくれますので、少し手を加えるだけで、自分らしいメッセージに仕上げることができます。
<活用例>
・候補者の経歴にマッチした個別メッセージ案の作成
・短くても印象に残る文章の草案
・企業の温度感に合った表現の調整(丁寧/カジュアル など)
③面接用の質問作成
採用すべき人材かどうかを見極めるために効果的な質問内容は、職種やポジション、求める人によって様々で、特に未経験の職種を担当するときや、新しいポジションの面接をする時は、質問の内容を考えるだけでもひと苦労です。状況に合った質問をいくつも提案してくれる生成AIを活用すれば、基本的な質問から深掘りの問いまで、会話の流れも想定した構成で出力してくれるでしょう。
<活用例>
・営業職向けの成果や工夫を引き出す質問
・エンジニア向けのスキル理解を深める技術的な質問
・マネジメント経験者向けのリーダーシップに関する質問
④候補者評価の要約・報告書の作成
面接後の報告や評価コメントの記入は、意外と時間がかかるものです。「なんとなく印象は覚えているけど、うまく言葉にできない」という時にも、生成AIが役立ちます。面接メモや音声の文字起こしなどをもとに、評価コメントの下書きや、候補者の強み・懸念点を整理した文章を提案してくれるので、報告書づくりがスムーズになります。
<活用例>
・メモをもとにした候補者の印象や評価の要約文
・他の面接官との共有用レポートの下書き
・合否の判断材料を分かりやすく整理した文面
⑤採用広報の草案作成
SNS投稿やブログ記事など企業の魅力を発信する広報活動も、採用においてはとても大切です。「何を書けばいいかわからない」「投稿のネタが尽きてしまった…」と悩んだ時には、ちょっとしたテーマや素材から記事の構成や投稿文の例を考えてくれる生成AIが発信のきっかけを作ってくれます。内容の幅が広がることで、採用ブランディングの強化にもつながります。
<活用例>
・社員インタビュー記事の導入文や質問案の作成
・SNS投稿用の140文字以内のキャッチーな文案
・社内イベントや社風紹介のブログ記事の下書き
3.採用業務で生成AIを使う4つのメリット
生成AIは、ただ便利なツールというだけでなく、採用業務の質とスピードを両立させる「新しい味方」としてさまざまなメリットをもたらしてくれます。ここでは、その代表的な4つのメリットをご紹介します。
①業務の時短・効率化ができる
採用業務では、日々さまざまな資料づくりや文面作成に追われることも多いかと思います。「伝わりやすい表現を考えるのに時間がかかる」「毎回同じような内容なのに手間はかかる」と感じたことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。生成AIを活用すれば、求人票や面接資料、スカウトメールなど、繰り返し発生する業務をテンプレート化しながらスピーディに処理することができます。これにより、担当者はより重要な「人を見る目」や「採用戦略の立案」といった本質的な業務に集中できるようになります。
②アウトプットの質の底上げが期待できる
「自分の言葉で書くと、どうしても表現がワンパターンになってしまう…」そんな悩みにも生成AIは力を発揮します。語彙や言い回しの選択肢を広げてくれるため、読み手に伝わりやすく、印象に残る表現を作ることができます。特に、文章作成が苦手と感じている方や経験値の少ない新人の採用担当者でも、一定レベル以上のアウトプットを安定して出せるようになる点は大きなメリットです。文章の精度が上がれば、求人の魅力もより的確に伝わり、応募率の向上にもつながります。
③採用活動のスピードがアップする
求人票の作成やスカウトメールの送信など、採用活動には「スピード感」が求められる場面が多くあり、せっかく良い人材を見つけても、対応が遅れて他社に先を越されてしまったという経験をされた方も少なくないはずです。生成AIを導入することで必要な文面や資料をその場でスピーディに作成できるようになり、選考の流れをスムーズに保つことができます。時間をかけずに一定水準の内容を整えることができるため、スピードと品質のバランスを両立することが可能になるのです。
④アイデア出しのサポート
広報コンテンツやSNS投稿、キャッチコピーづくりなど、採用活動には「発想力」が求められる場面で、生成AIは“考えるきっかけ”を与えてくれます。いくつものアイデアを一気に出してくれるので、それを見ながら自分なりの工夫や言葉を加えていくことで、より魅力的な発信が可能になります。ゼロから考えるよりもぐっと楽に、かつ創造性の幅を広げることができるのも魅力です。
4.採用業務で生成AIを使う4つのデメリット
採用活動をサポートする頼もしいツールである一方、活用の際には注意しておきたいポイントもあります。ここでは、考えられる4つのデメリットについてご紹介します。
①出力内容の正確性に不安がある
生成AIは、「もっともらしい表現をつくること」が得意な技術です。しかし、その反面、事実に基づいていない情報が含まれる場合があります。存在しない制度や誤ったデータを含んだ文章が出力されることもあり、これは「AIのハルシネーション」と呼ばれる現象の一例です。そのため、求人情報や評価コメントなど、正確性が求められる文章を扱う場面では注意が必要です。生成された文章をそのまま使うのではなく、最終的には人の目でチェックし、事実との整合性を確認することが不可欠です。
②情報漏えいのリスクがある
生成AIはクラウド上で動作していることが多いため、入力した内容が外部のサーバーに送信される仕組みになっています。採用業務では、候補者の氏名や経歴、選考に関する評価など、機密性の高い情報を取り扱う場面が多いため、安易にAIへ入力してしまうと情報漏えいにつながる恐れがあります。こうしたリスクを回避するためには、入力内容をあらかじめ精査し、個人情報や社内機密に関わる情報は含めないという基本的なルールづくりが必要です。また、社内でのガイドライン整備や教育も併せて進めることで、より安全な運用が実現できます。
③ニュアンス・企業らしさの表現が不十分になる可能性
生成AIが生み出す文章は、読みやすく整ったものが多い反面、どうしても画一的で無難な印象になりがちです。そのため、自社らしい言葉づかいや採用担当者ならではの熱意、温かみといった“ニュアンス”が十分に伝わらないケースもあり、温度感や感情のこもった表現は、やはり人ならではの言葉で補うことが必要です。AIの文章をベースにしつつ、企業の個性を加えることが、読み手に響く発信につながるのです。
④活用スキルの差が出る
生成AIは、「どんな指示を与えるか」によって出力される内容が大きく変わります。そのため、活用する人のスキルや経験によって得られる成果にばらつきが出やすいという側面があり、目的があいまいなまま使った場合には期待していたような内容が出てこなかったり、逆に修正に時間がかかってしまったりすることもあるでしょう。また、「どのように入力すれば、より良いアウトプットが得られるか」といったノウハウを持たないまま導入すると、効果が十分に発揮されないこともあります。
5.生成AI活用のコツ
ここでは、採用業務で生成AIを活用する際に意識しておきたい4つのポイントについて解説します。
①プロンプト設計を工夫する
生成AIに何かを依頼する際には、最初に入力する「指示文(=プロンプト)」の質が結果を大きく左右します。たとえば、「求人票をつくって」とだけ伝えるのではなく、「20代の営業未経験者に向けて、未経験でも安心して働けることを伝えたい」「企業のアットホームな雰囲気が伝わるようにしたい」といった背景や目的、想定読者まで伝えることで、より的確で自社に合った文章が生成されやすくなります。少し慣れてくると、こちらの意図を伝えやすい指示の感覚もつかめてきますので、まずはいくつか試してみるのがおすすめです。社内での活用事例を共有したり、簡単な使い方マニュアルや指示定型文を作成したりして、誰でも効果的に使えるようなベースを整えましょう。
②AIの出力は“たたき台”と考える
AIが出力する文章は、完成品ではなく“下書き”としてとらえるのが理想的です。一見するときれいにまとまっているように見えても、自社の方針や実態とズレている部分があったり、トーンがやや堅すぎたりカジュアルすぎたりすることもあります。AIが作った文章をそのまま使うのではなく、担当者自身の目線で必要な修正を加えることで、初めて“伝わる”コンテンツに仕上がります。
③情報管理を徹底する
生成AIはインターネット経由で処理される仕組みが一般的であるため、入力した情報が意図せず外部に渡る可能性がゼロではありません。特に、候補者の氏名や連絡先、社内での評価内容など、個人情報や機密情報を直接AIに入力することは避けるべきです。安心して活用を進めるためにも、「何を入力してよくて、何は控えるべきか」といった社内ルールを明確にしておくことが重要です。社内で活用を広げていく場合には、簡単なガイドラインやチェックリストを用意し、誰でも安全に活用できる環境を整えましょう。
④人によるチェックを必ず入れる
生成AIがつくった文章には、一見もっともらしいけれど実は事実と異なる内容が含まれていることがあります。また、読み手にとってわかりづらい表現や、自社の雰囲気に合わない言い回しが含まれている場合もあります。出力された内容は必ず人の目でチェックし、「正しいかどうか」「読みやすいか」「自社らしいか」という観点で確認・調整を行いましょう。この一手間をかけることで、信頼される情報発信につながります。
6.まとめ
生成AIは、使い方次第で採用業務の心強いパートナーになります。最初は小さな業務から少しずつ使いはじめて、試行錯誤を重ねることで、自社に合った活用スタイルが見えてくるはずです。まるごとAIに任せてしまうのではなく業務のサポート役として上手に活用することで、業務の負担を軽減すると共に、表現の幅が広がや、発信力の向上にもつながりスピードも質も両立したアウトプットが可能になります。迷ったときや困ったときは、社内での共有や、外部の支援も活用しながら取り入れてみてはいかがでしょうか。
福島採用.comでは、高卒採用に関するデータレポートやお役立ちコラムの他、高卒採用活動に役立つ各種ツールの相談も随時受け付けています。「高卒採用がうまくいかない」「応募を獲得するためにいい施策はないだろうか?」などのお悩みがありましたら、いつでも気軽にご相談ください。