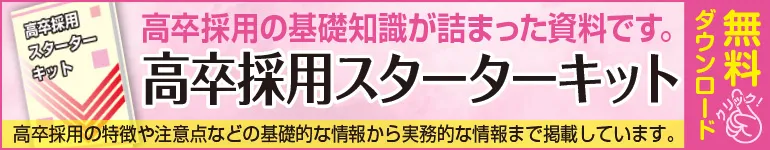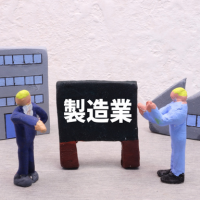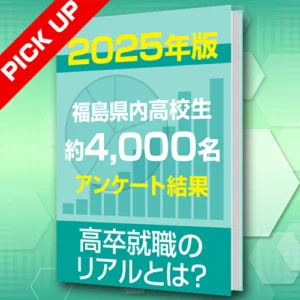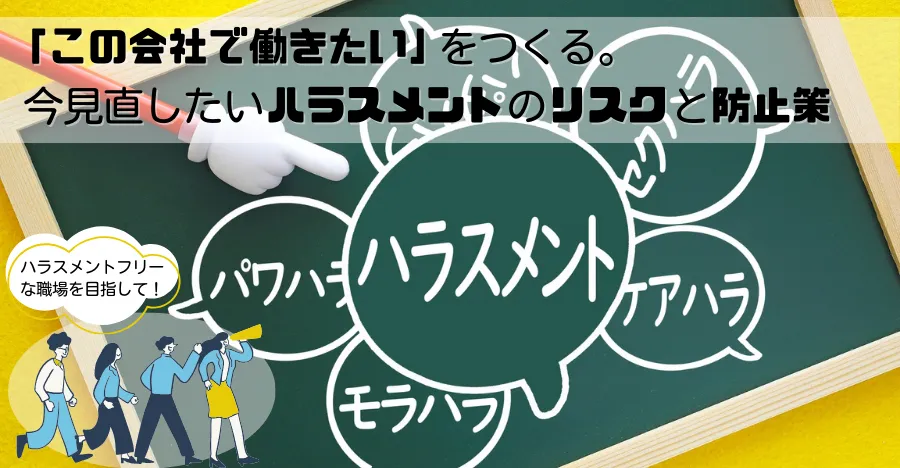
近年話題の「ハラスメント」は、被害者の心身に深刻な影響を及ぼすと共に組織全体の生産性や信頼性を低下させる大きな要因となる大きな社会問題です。本記事では、ハラスメントの定義や種類、企業への影響、発生時の対応策、防止策について解説します。
目 次
1.はじめに
2.ハラスメントの定義
3.よくあるハラスメント一覧
4.ハラスメントが企業に与える4つの損失
5.ハラスメント防止策5選
6.ハラスメント発生時の4つの手順
7.まとめ
1.はじめに
近年、職場を始めとするあらゆる場面で「ハラスメント」という言葉を耳にする機会が増えています。一見些細に思える言動が、相手にとっては深い傷となり、精神的・肉体的な苦痛を与えることもあります。ハラスメントは単なる人間関係のトラブルではなく、企業の信頼や組織の生産性を脅かす重大な社会問題です。本コラムでは、ハラスメントの定義や種類、企業が講じるべき防止策などをわかりやすく解説します。
2.ハラスメントの定義
ハラスメントとは、他者に対する不適切な言動や行為により、相手の尊厳を傷つけたり、不快感や不利益を与えたりする行為を指し、職場や学校、日常生活のあらゆる場面で発生する可能性があり近年社会問題として注目されています。被害者や組織に大きな悪影響を与えるだけでなく、すべてのハラスメントは民法の不当行為(故意・過失によって他人の権利や法律上の利益を侵害する行為)に該当する場合があります。ハラスメントには、法令で定義されているものとそうでないものがあり、
「パワハラ」「セクハラ」「マタハラ」「パタハラ」「ケアハラ」
以上の5つは法令により定義され、企業に対して防止措置の実施が義務付けられています。
(参考:厚生労働省 職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント))
その他法令では定義されていないものも多くありますが、いずれも加害者の意図に関わらず相手の受け取り方によって判断されることが特徴であり、一度きりの行為でも継続的な行為でもハラスメントとなり得ます。
3.よくあるハラスメント一覧
ハラスメントには様々な種類が存在し、以下のようなものが代表的です。
①セクシュアルハラスメント(セクハラ)
性的な言動や身体的な接触により、不快感や不利益を与える行為です。男女雇用機会均等法およびそれに基づく指針にて定義され、事業主に防止措置が義務付けられています。
【具体例】
・同僚に性的な冗談や下ネタを頻繁に言う。
・飲み会の席で体に不必要に触れる。
・「そんな格好じゃモテないよ」と容姿を性的な目線で評価する。
②パワーハラスメント(パワハラ)
職場の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて精神的・身体的苦痛を与える行為です。労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が施行され、2022年4月からは企業規模を問わずすべての事業主に対して対策が義務付けられています。
【具体例】
・業務に関係ないことで大声で叱責し続ける。
・他の社員の前で何度も失敗を晒して侮辱する。
・気に入らない部下にだけ過剰な仕事を押し付ける。
③マタニティハラスメント(マタハラ)
妊娠・出産・育児休業等を理由とした不利益な扱いや嫌がらせのことを指します。2017年施行の改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法にて、事業主に防止措置が義務付けられました。
【具体例】
・妊娠を報告したら「仕事に穴をあけるな」と嫌味を言われる。
・産休・育休の取得を上司から反対される。
・妊娠したことを理由に出世コースから外される。
④パタニティハラスメント(パタハラ)
男性従業員の育児に関する嫌がらせです。マタハラと同様に、改正男女雇用機会均等法、改正育児・介護休業法にて、事業主に防止措置が義務付けられました。
【具体例】
・男性社員が育休を申し出ると「男なのに?」と非難される。
・育休明けに重要なプロジェクトから外される。
・子どもの保育園迎えで早退すると「家庭を優先するな」と責められる。
⑤ケアハラスメント(ケアハラ)
介護休業を取得する、あるいは希望する労働者に対する不利益な取扱いや嫌がらせです。「ケアハラ」という言葉自体はまだ法律上明確に定義されていませんが、育児・介護休業法において介護に関わるハラスメントの防止措置も対象とされています。
【具体例】
・親の介護のための時短勤務を希望したら「仕事に専念できないなら辞めろ」と言われる。
・介護での早退や休みに対し、同僚から文句を言われる。
・介護を理由に昇進のチャンスを奪われる。
⑥モラルハラスメント(モラハラ)
倫理・道徳に反する言葉や態度等による精神的な嫌がらせのことを指します。
【具体例】
・無視や皮肉など、直接的ではないが継続的に精神的に追い込む言動。
・「君は何をやってもダメだ」と人格を否定する。
・常に否定的な言葉をかけ、相手の自信を奪う。
⑦ジェンダーハラスメント(ジェンハラ)
性別に関する差別的な言動や行為です。
【具体例】
・「女性には難しい仕事だ」と性別で役割を決めつける。
・「男ならもっと稼げ」と圧力をかける。
・性別を理由に会議で発言を無視される。
⑧テクノロジーハラスメント(テクハラ)
IT技術や最新テクノロジーなどに関する嫌がらせです。
【具体例】
・ITツールの使い方がわからない人を馬鹿にする。
・新しいシステムに対応できない中高年社員を排除するような態度をとる。
・ITスキルが低い人に対してわざとIT業界の専門用語を使って話をする。
⑨アルコールハラスメント(アルハラ)
飲酒に関する強要や不適切な扱いのことを指します。企業においては、職場の飲み会の席で発生することが多いです。
【具体例】
・飲み会で飲酒を強要する。
・酔った勢いでの暴言やセクハラ発言。
・アルコールを断るとチームの和を乱すと言われる。
⑩ハラスメントハラスメント(ハラハラ)
正当な行為に対して過剰に反応して嫌がらせを行うものです。
【具体例】
・ハラスメント対策を逆手に取り、上司を萎縮させる。
・被害者を装って会社に圧力をかけ、自分に有利に動かそうとする。
4.ハラスメントが企業に与える4つの損失
ハラスメントは、企業に以下のような損失をもたらす可能性があります。
①生産性の低下
ハラスメントが発生すると、被害者だけでなく周囲の従業員のモチベーションや業務に対する集中力の低下、職場の雰囲気悪化からチームワークやコミュニケーションに支障が生じ、ミスの増加や業務の停滞を招きます。その結果、組織全体の生産性が大きく落ち込み、目標達成にも悪影響を及ぼします。
②人材の流出
ハラスメントを受けた従業員が退職するだけでなく、職場環境に不安を感じた他の社員まで離職する恐れがあります。特に、優秀な人材ほど働きやすさを重視するため、早期に転職を検討する傾向があります。一度に複数の人材が流出すれば、組織力の低下や業務の継続に支障が出るうえ、採用・育成にかかるコストも増加します。
③企業イメージの悪化
ハラスメント問題が報道や口コミなどで明るみに出ると、企業の社会的信用が大きく損なわれます。消費者や取引先からの信頼が低下し、取引中止や売上減少につながる可能性もあります。さらに、就職希望者の減少やSNS上での批判拡散により、企業ブランドの価値も下がり、長期的な経営リスクとなりかねません。
④法的リスク
被害者から訴訟を起こされた場合、企業は損害賠償や慰謝料の支払いといった金銭的負担を負う可能性があります。加えて、行政指導や是正勧告を受けることもあり、社会的信用を大きく損なう結果となります。裁判で社内事情が公開されれば、企業イメージへのさらなる悪影響や経営陣の責任問題にも発展しかねません。
5.ハラスメント防止策5選
ハラスメントを未然に防ぐためには、企業全体での継続的な取り組みが必要です。
①明確な方針を策定・周知する
ハラスメントを防止するためには、企業としての明確な姿勢を示すことが重要です。就業規則や社内ガイドラインに防止規定を明記して全社員に方針を周知徹底することで、許されない行為であるという認識を共有します。組織としての毅然とした対応姿勢が、抑止力となるのです。
②研修や教育を実施する
新入社員の研修に組み込んだり管理職を対象に定期的な教育を実施したりすることで、ハラスメントに対する正しい知識と意識を高めます。特に管理職には、未然防止や早期対応の役割があることを理解させることが重要です。事例を交えた実践的な内容にすると、より当事者意識を持たせやすくなり効果的です。
③相談窓口を設置する
被害者が安心して相談できるよう、社内外に複数の相談窓口を設置しましょう。窓口の存在を周知し実際に機能する体制を整えることで、問題の早期発見と対応が可能になります。相談内容の秘密保持を徹底し、報復を恐れずに声を上げられる環境をつくることが大切です。
④職場環境の改善
日常的なコミュニケーションの活性化や意見を言いやすい雰囲気作りを通じて、風通しの良い職場環境を目指すことが大切です。上司と部下の信頼関係を築くことは、ハラスメントの大きな抑止力になり得ます。定期的な面談や職場アンケートの実施など、現場の声を拾う工夫も有効です。
⑤再発防止のためのPDCAサイクルを整える
ハラスメント事案が発生した場合には、原因を的確に分析し再発防止策を立案・実行することが重要です。その後、取り組みの効果を評価・見直しすることで、組織として継続的な改善が可能になります。PDCAサイクルを回すことで、一時的な対応にとどまらない実効性のある対策を実現できます。
6.ハラスメント発生時の4つの手順
ハラスメントが発生した場合、企業は次の手順に沿って対応を迅速かつ適切に行う必要があります。
事実関係の確認→被害者への支援→加害者への対応→再発防止策の実施
以下、各手順を詳しく解説します。
①事実関係の確認
ハラスメントが発覚した際は、まず当事者や関係者への丁寧な聞き取り調査を実施し、客観的な事実関係を正確に把握する必要があります。曖昧な判断を避けるためにも、記録や証言などをもとに状況を多角的に検証することが大切です。調査は公平・中立な立場で行い、関係者のプライバシーにも十分に配慮することが求められます。
②被害者への支援
被害者に対しては、心身のケアを最優先に考えた支援が最も重要です。カウンセリングの紹介や、必要に応じた業務の見直し・配置転換などを通じて、負担を軽減し安心して働ける環境を整える必要があります。また、再被害の防止や報復行為への対策も講じることで、被害者の不安を和らげる対応が求められます。
③加害者への対応
ハラスメント行為を行った者には、行為の内容や影響の程度に応じて適切な処分を検討します。口頭での注意や書面での警告から、減給、出勤停止、降格、最終的には懲戒解雇まで、就業規則に基づいた対応が必要です。また、加害者本人に対しても教育や指導を行い、再発を防ぐ意識付けを行うことが望まれます。
④再発防止策の実施
ハラスメントを一度の問題として終わらせず、再発防止に向けた継続的な取り組みを行いましょう。職場の雰囲気や組織体制の見直しや必要な改善を加え、従業員全体への意識啓発を継続して実施します。具体的には、研修の強化やガイドラインの見直しなどを通じて、同様の事案を繰り返さない環境作りを行います。
7.まとめ
ハラスメントは、被害者個人の尊厳を傷つけるだけでなく、企業全体の雰囲気や信頼性、業績にも深刻な影響を与える問題です。まずは「何がハラスメントに該当するのか」を知ることが出発点であり、ルール作りや教育・研修、相談体制の整備など、組織としての包括的な対策が求められると共に、一人ひとりの意識改革も重要です。誰もが安心して働ける職場環境作りは、生産性や企業の持続的成長にも直結する“未来への投資”と捉え、企業全体で取り組んでいくことが求められているのです。
福島採用.comでは、採用に関するお役立ちコラムの他、採用活動で使える各種ツールの相談も随時受け付けています。「優秀な人材を採用したい」「効果的な採用活動について知りたい」などのお悩みがありましたら、いつでも気軽にご連絡ください。